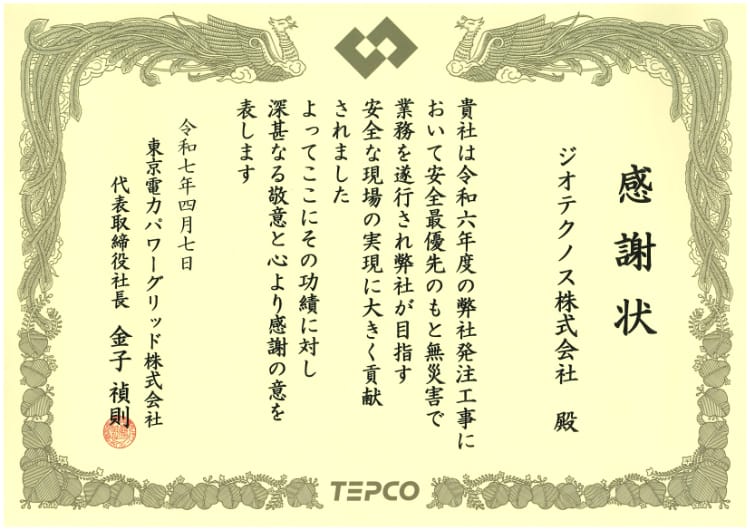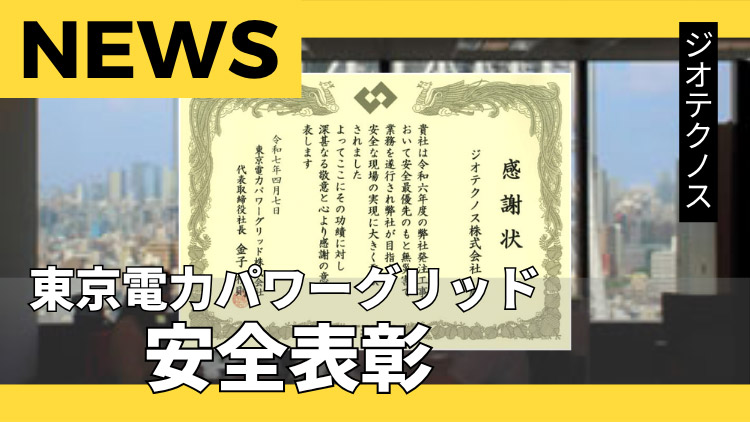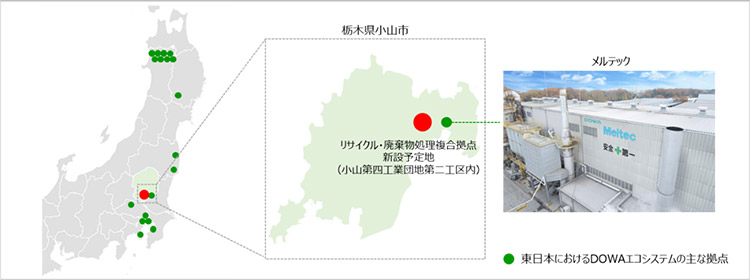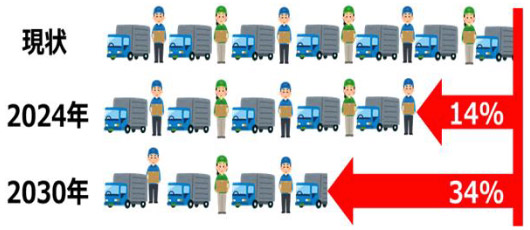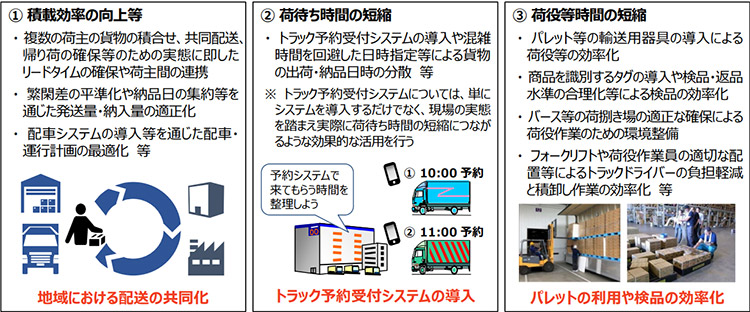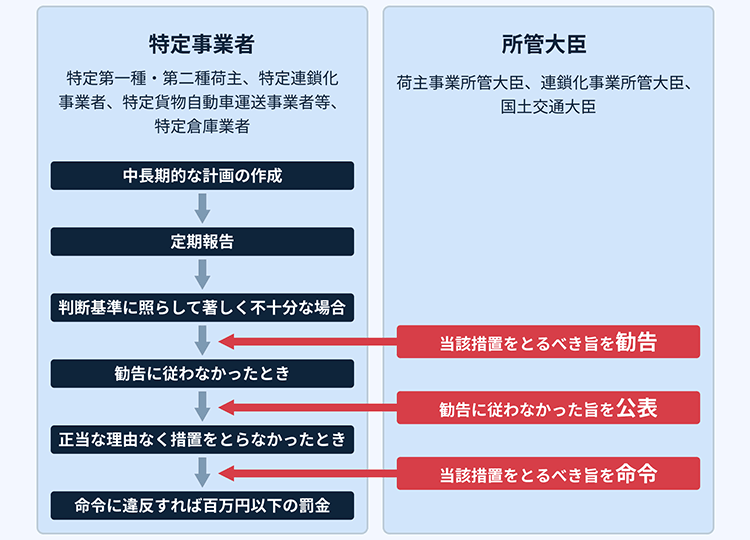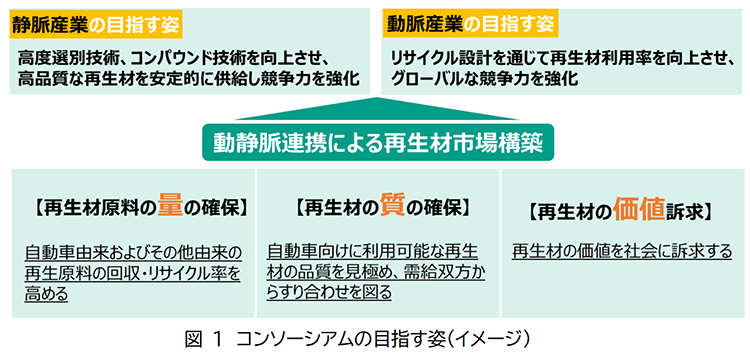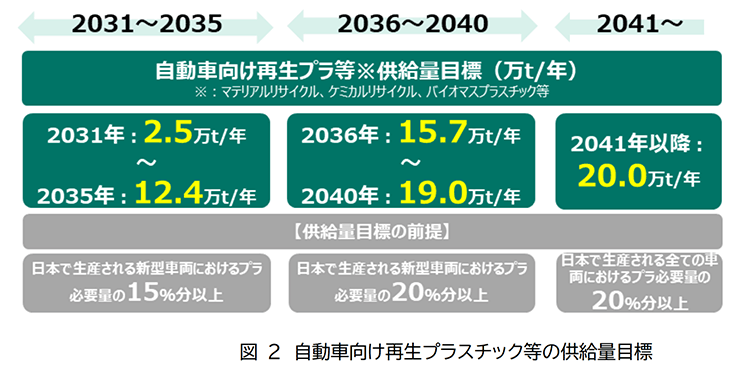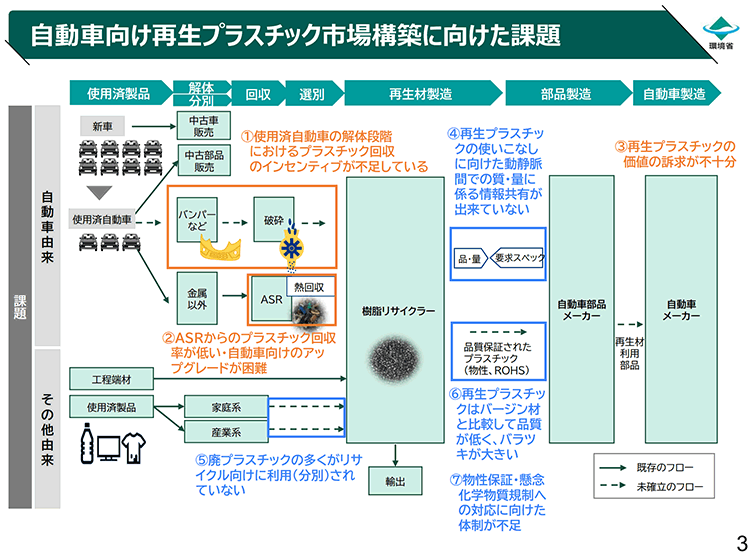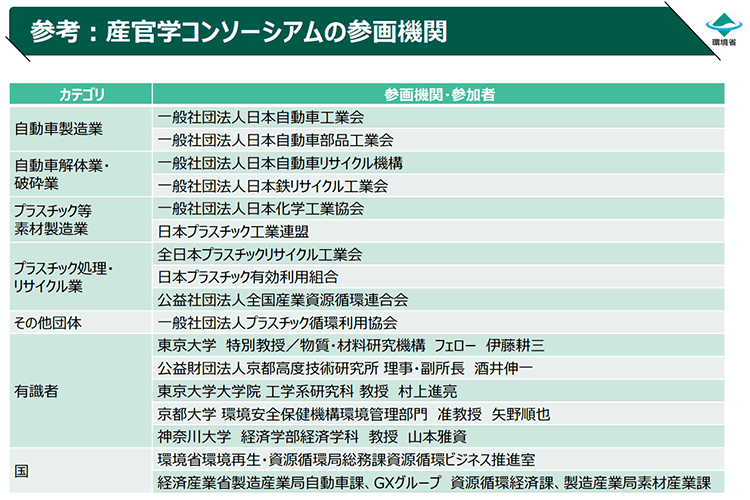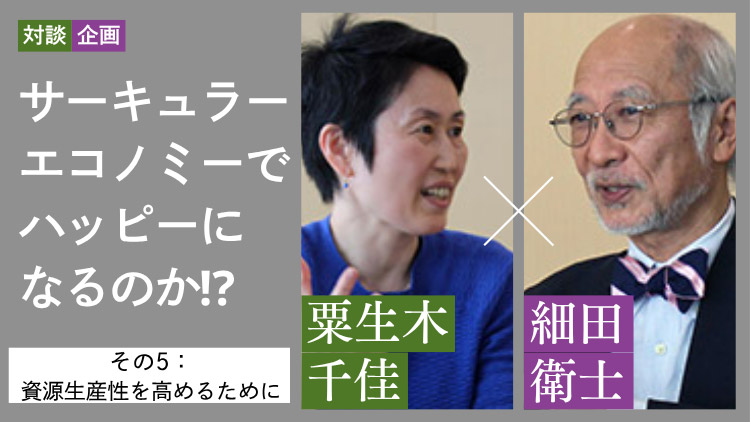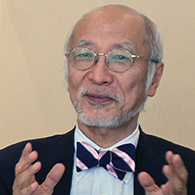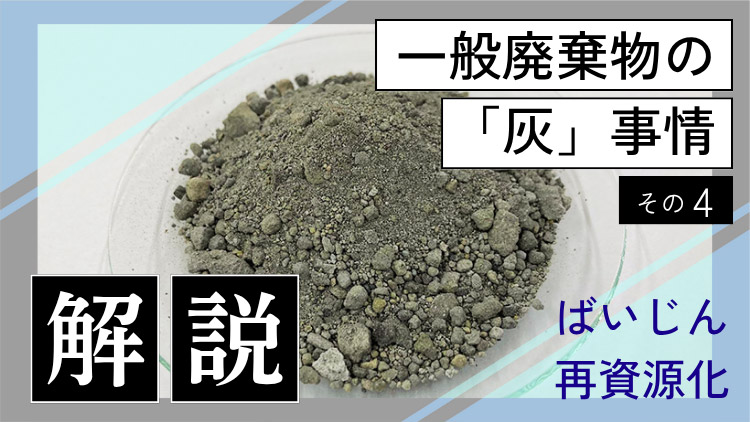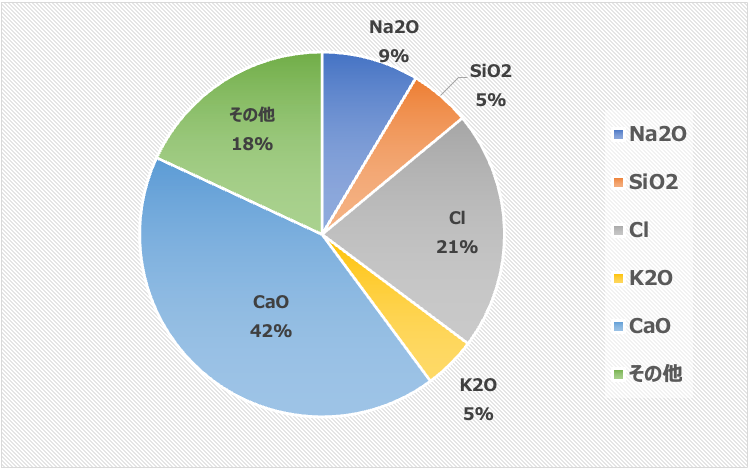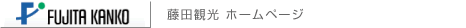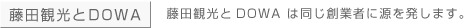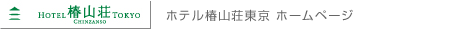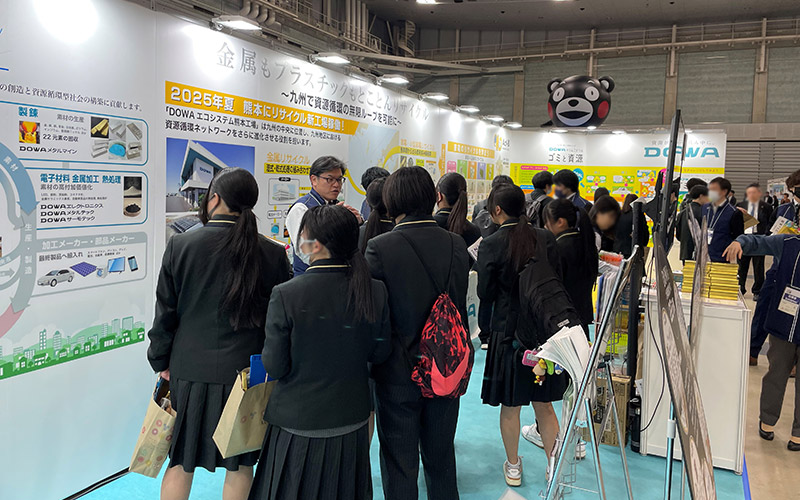今日ご紹介するごみ処理事情は、お隣の国・韓国。
私が住んでいる京畿道東部に位置するイチョン市は、お米と陶磁器が有名で、ソウルまで電車で1時間ほどのベッドタウンです。
文化面など日本と似たところのある韓国ですが、果たしてごみ処理事情も似ているのでしょうか。なかなか知る機会のない韓国のごみ処理事情について、ご紹介していきます。
■家庭ごみは大きく分けて3つ
韓国の家庭ごみの分別は日本とよく似ていて、「生ごみ」「一般ごみ」「リサイクル」の3つに分かれます。
自治体によって異なりますが、ソウルや近郊の都市であれば、生ごみは平日であれば毎日回収、一般ごみは週に2~3回、リサイクルの分別ごみは週に1~2回、回収されます。
■ごみの捨て方・頻度は建物ごとに異なる
韓国では、建物ごとにごみの捨て方や頻度が異なります。
一軒家や「ビラ」と呼ばれる5階建ての住宅の場合は、その近隣のごみ捨て場に、決まった曜日にごみを捨てるルールになっています。これは日本のごみ捨てルールに近いかもしれません。

生ごみやプラスチックなど、すべてのごみを捨てられるよう、地域のまとめられている収集場はこんな感じです。

捨てる場所だけ決まっていることも。その場合は衛生面から、生ごみの回収ボックスは最低限置いてあります。
一方で「アパート」と呼ばれる高層マンションの場合は、そのマンション団地内でルールが決まっていることが多いです。
■365日いつでもごみを捨ててOK
私の住んでいるマンションでは、大きなごみ捨て場が2カ所あり、365日いつでもごみを捨ててOKとなっています。
特に魚など臭いのきついものを食べた日は、朝まで待たずに生ごみを処理できるので、非常にありがたいです。
捨てるタイミングは早朝でも深夜でも、本当にいつでも大丈夫なのですが、あくまで回収は平日のみ。そのため特に夏場、週末~月曜の朝、連休中のごみ捨て場は…カオスな状態になっていることも多々あります。
■生ごみの捨て方
前述した通り、ごみの捨て方や頻度は住んでいる地域や、建物によって異なります。特に、生ごみの捨て方に違いが見られます。
指定のビニール袋で捨てる
一軒家やビラの場合は、自治体が指定する「生ごみ専用」のごみ袋で捨てます。捨て方はそのままビニールにごみを直接いれてOKです。
カードで計量精算
マンションの場合は、ごみ捨て場に大型の生ごみ回収ボックスがあり、そこに捨てに行きます。では早速行ってみましょう。

生ごみは何回分かバケツにためています。生ごみ自体は、そのままバケツに入れて運搬する人もいますが、私は使い古したビニール袋に入れています。

回収ボックスは計量精算システムのため、お金をチャージしたカードを忘れず持っていきます。ちなみにこのカードは生ごみ専用というわけではなく、バスカードとしても使えるものです。

(写真左)回収ボックスにカードを入れると、フタが開き、生ごみを入れます。私のようにバケツ直ではなくビニールを使っている人のための「生ごみ用ビニール捨てボックス」も近くに置いてあります。
(写真右)ボタンを押すと、フタが閉まり「何グラムでいくらです」とアナウンスがあるので、残高を確認、カードを取ったら完了です。
とても便利なシステムなのですが、唯一の欠点が、このカードを取り忘れて失くすこと…。これまでに2回紛失しています…。

ごみ捨てボックスの隣には洗い場(画像右)もあり、真冬以外は利用できます。住民がスポンジや洗剤を持ち込んでいたり、夏場は防虫スプレーも常備されていたりもします。
■一般ごみは指定のビニール袋に入れて
一般ごみは回収頻度の違いこそあれ、捨て方は自治体や建物によって差はありません。自治体の指定するビニール袋に入れて、指定の場所に捨てるだけです。指定のビニール袋はスーパーなどで購入できますし、買い物の際に買ったものを入れるために1枚ずつ購入することも可能です。

マンションではこうした大型のボックスが設置されており、中に入れておくだけ。臭いの漏れや、ねずみなどに荒らされる心配がありません。
■リサイクルは分別して捨てる
びんやカン、プラスチックなどのリサイクルごみは、日本と同様に分別して捨てる必要があります。リサイクルごみについては韓国では指定のごみ袋はなく、各家庭で段ボールや室内ごみ箱にためておき、いっぱいになったらごみ捨て場に持ち込み捨てるのが一般的です。
一軒家やビラの場合は、その地域のリサイクルごみ捨て場、マンションの場合は、同じものが敷地内に設置されているので、自分で分別して捨てます。
では、私のマンションの分別ごみの状況を、写真でレポートします。
 写真左から:プラスチック/ビニール/発泡スチロール
写真左から:プラスチック/ビニール/発泡スチロール
 写真左から:カン/びん/段ボール
写真左から:カン/びん/段ボール
 写真左から:衣類のリサイクルボックス/電球回収ボックス/乾電池回収ボックス
写真左から:衣類のリサイクルボックス/電球回収ボックス/乾電池回収ボックス
■まとめ
以上、韓国のごみ処理事情についてお届けしました。
日本と似ている点もありながら、「パリパリ(早く早く)」文化の韓国らしい、効率重視な面も垣間見えるごみ処理事情、いかがでしたか?
写真を見ていただくとわかるかもしれませんが、韓国の分別ルールはわりと「ざっくり」している部分も多いです。日本で厳しく分別教育を受けてきた身としては、いまだに「これはどこに捨てるの……?」「もう少しきちんと分別しないとリサイクルできないのでは……?」と戸惑うこともあります。
一方で、時間や曜日を気にせずごみが捨てられるのは、本当に便利な制度です。また、街中や公園などいたるところにごみ箱があるので、ごみを持ち帰るという習慣がなくなりました。こうして行政によってこまめに管理されています。
 この記事は
この記事は
フリーランスライター Sun Chisako が担当しました