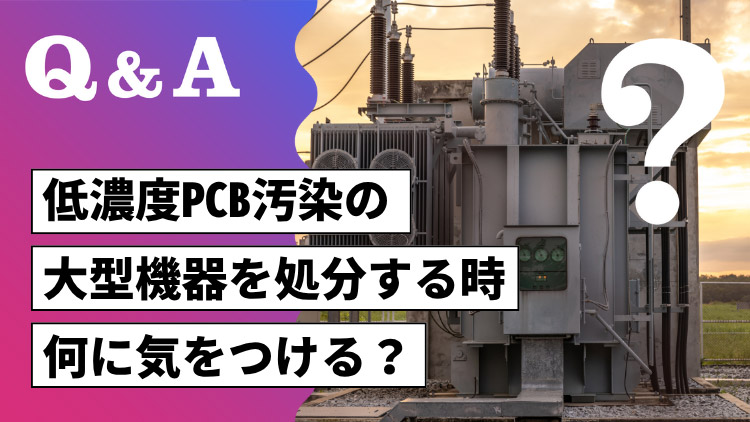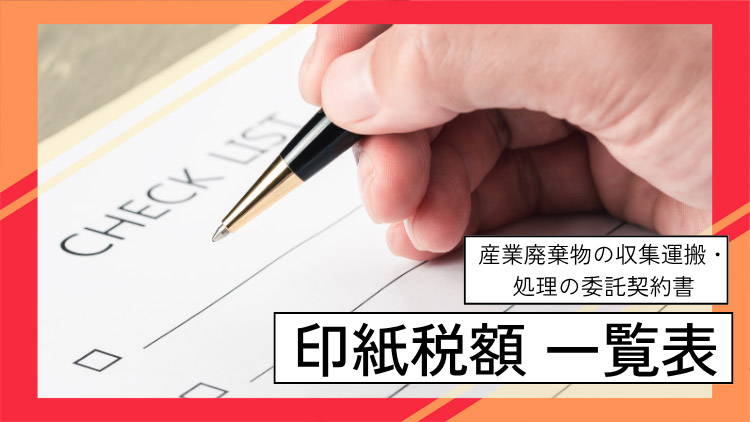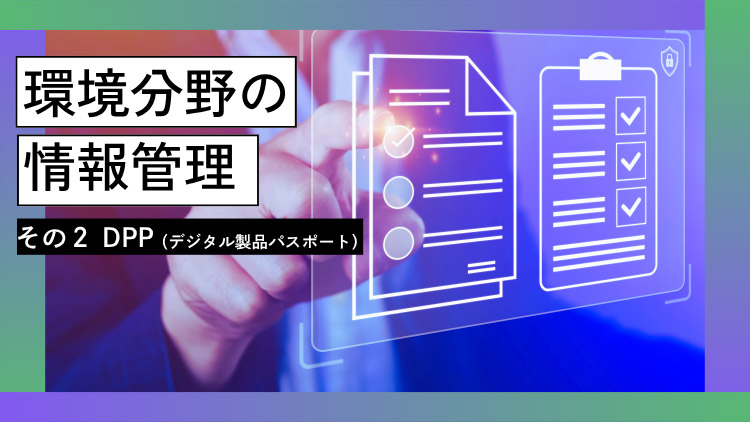Q:低濃度PCBに汚染された、大型機器を処分する際に気をつけることはありますか?
- A:
-
解体する大型機器や設置現場の状況に応じたPCBの拡散防止対策や火災対策はもちろんですが、全体の進行管理の体制についても検討しておくことをお勧めします。
■はじめに
低濃度PCBに汚染された筐体の処分には、3つの方法があります。
- 解体せずに搬出
- 現地で洗浄処理
- 現地で解体した後に搬出
| 解体せずに搬出 | 現地で洗浄処理 | 現地で解体した後に搬出 | |
|---|---|---|---|
| 一般的な対象 | 小型~中型の変圧器等、トラックに積載可能、処理工場が受け入れ可能な大きさのもの | 大型のもので、トラックへの積載が難しいもの | |
| メリット・デメリットなど | 特別車両をチャーターして大型の機器を搬出することも可能だが、処理工場にて投入可能なサイズに解体される。 | 洗浄に期間がかかる。浄化が確認されるまで洗浄するため、洗浄回数にコストが左右される。洗浄回数が少ない場合は安価だが、回数が多くなる場合には、高額になるケースある。 洗浄に用いたPCBを含有する油の処分が必要。 洗浄を実施する前に大臣認定の取得が必要。 |
洗浄に比較して処分完了までの期間は短い。 解体工事中のPCBの飛散・漏洩に注意をする必要がある。 処理工場で処理可能なサイズに解体されているので、処理のための搬出がスムーズ。 |
今回は、現地で解体した後の搬出する際、どんなリスクがあり、どのような対策が必要なのかについて、ご説明します。
■現地解体後の搬出で気を付けるポイント
現地で解体した後に搬出する場合の、大まかな流れは、以下の通りです。
【事前準備】
現地確認→計画・費用見積
【着 工】
現場の養生→解体工事→運搬→処分
大型機器の解体、PCB汚染廃棄物の運搬、PCB汚染物の処分については、ガイドラインが環境省から公開されており、ガイドラインに則って実施する必要があります。
(参考)ポリ塩化ビフェニル廃棄物に関する各種ガイドライン等(環境省)
ガイドラインはありますが、ガイドラインを踏まえつつ、状況からリスクを判定して、どの程度の対策が必要か検討する必要があります。

(周辺環境への汚染のリスク)
- 作業現場の地面の養生のスペック
- 作業現場周辺の仮囲いの有無・スペック
- 養生するエリアの範囲
(火災のリスク)
- 筐体の切断工法のスペック
(運搬途中の漏洩リスク)
- 運搬の際の漏洩対策(運搬容器の密閉性など)
- 過積載対策、事故防止対策
(管理)
- 元請事業者職員の役割
- 発注者への報告頻度
- 安全・品質管理に関する工程管理方法
処分する低濃度PCB汚染機器や、解体工事を行う現場の状況に応じて、適切な対策を行う必要があります。

こうした安全へ配慮した工夫や改善が評価され、2023年6月と2024年4月に、ジオテクノスが、東京電力パワーグリッド株式会社より表彰を受けました。
関連記事(NEWS)
ジオテクノスがPCBで汚染された大型変圧器の解体運搬業務に関して「東京電力パワーグリッド工務部安全表彰」を受けました
東京電力パワーグリッドより安全表彰を受けました
■全体進行管理
大型機器を現地で解体してから運搬する場合、工事と運搬と処分とが並行して行われます。
工事の進捗に合わせて、運搬容器を現場に搬入し、解体の状況に合わせて運搬会社に車両を手配する必要がありますし、処分を委託する数量も多いので、処理会社側といつ・どのくらい受け入れが可能なのかについて調整をし、場合によっては、工事の進捗と調整する必要が生じる場合もあります。
解体工事を行う会社と運搬会社、処分会社が異なる場合、排出事業者が各社に情報を提供し、各社とスケジュール調整を行う必要がありますが。DOWAグループでは、エコシステムジャパンがこうした一連の調整を行い、安全な施工とスムーズな搬出を実現します。

こうした実績を評価していただき、2025年4月にエコシステムジャパンが、東北電力ネットワーク株式会社秋田支社より表彰を受けました。
関連記事(NEWS)
東北電力ネットワークより安全な処理に関する表彰を受けました
■さいごに
低濃度PCB廃棄物の処理が始まって15年、低濃度PCB廃棄物の処理件数は増え、環境省よりガイドラインが公開され、低濃度PCB廃棄物の解体・運搬・処理は確立されたものとなってきました。
一方で、PCBはひとたび漏洩すると、周辺環境へ被害を与える恐れがあり、自治体や住民の方々への説明、漏洩したPCBの除去工事など、様々な影響が生じます。
DOWAエコシステムグループは、これまで実施した大型機器の解体工事の知見を活かし、現場、現物、排出事業者のご希望などに合わせ、適切なプランニングを行います。
![]() この記事は
この記事は
エコシステムジャパン株式会社 上田 が担当しました