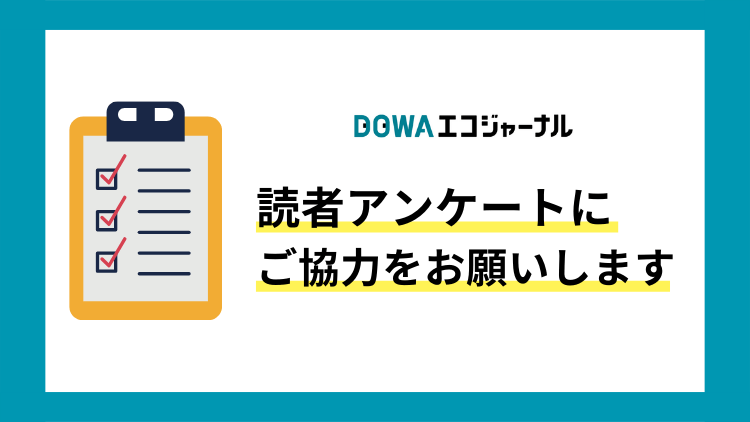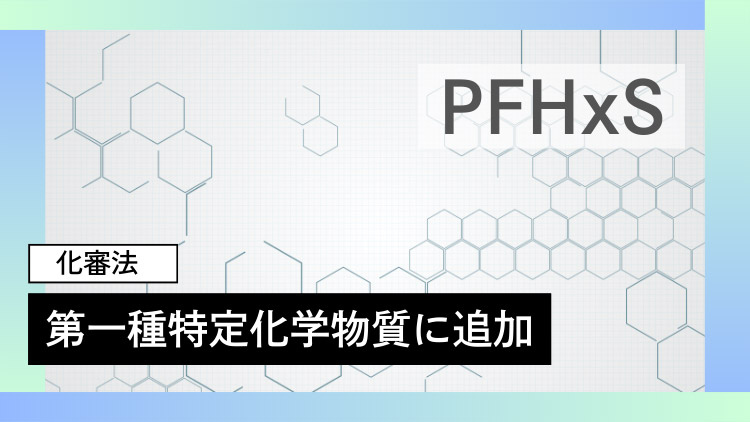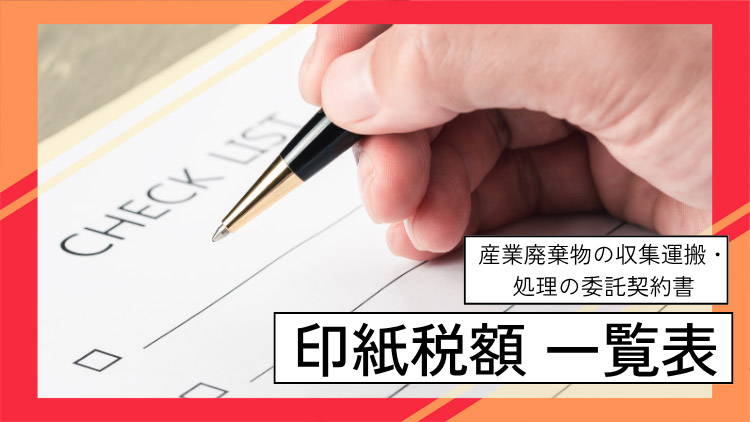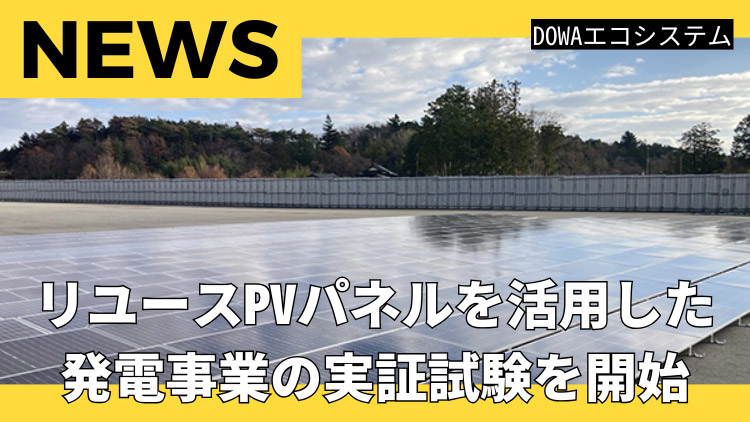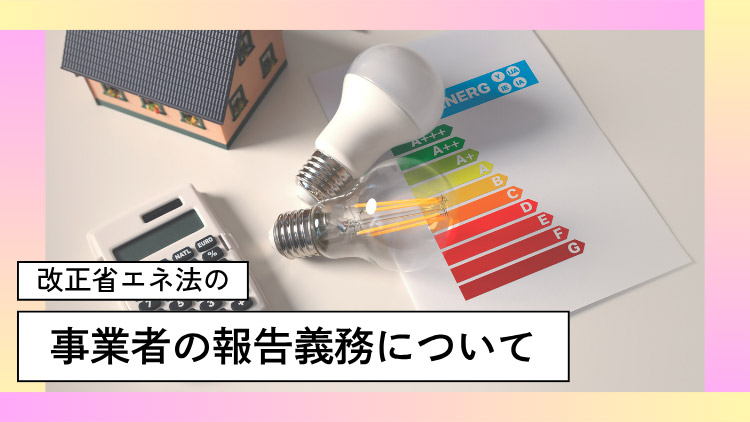(廃棄物の)再委託(廃棄物処理法)
さいいたく(はいきぶつしょりほう)
廃棄物処理業者が、排出事業者から処理を委託された廃棄物を他人に委託すること。
一般廃棄物は廃棄物処理法第7条第14項で、産業廃棄物は廃棄物処理法第14条第16項で、それぞれ再委託が禁止されている。ただし産業廃棄物については、政令で定める基準に従って委託する場合及び環境省令で定める場合は、一度に限り再委託が認められる。
例えば、産業廃棄物の収集運搬トラックが急な故障や事故によって動かなくなってしまい、他の収集運搬会社のトラックで運搬せざるを得ないような場合、収集運搬業者は、あらかじめ排出事業者から書面で承諾を受ける等、再委託の基準(廃棄物処理法施行令第6条の12、廃棄物処理法施行規則第10条の7)を守って収集運搬の再委託をすることができる。
なお、一般廃棄物については再委託は認められない。
【参照条文】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
第7条 第14項
一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。
第14条 第16項
産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
(昭和四十六年九月二十三日政令第三百号)
第6条の12
法第十四条第十六項 ただし書の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一
- あらかじめ、事業者に対して当該事業者から受託した産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者(以下「再受託者」という。)の氏名又は名称(法人にあつては、その代表者の氏名を含む。)及び当該委託が第六条の二第一号又は第二号に掲げる基準に適合するものであることを明らかにし、当該委託について当該事業者の書面(環境省令で定める事項が記載されたものに限る。)による承諾を受けていること。
- 二
- 再受託者に当該産業廃棄物を引き渡す際には、その受託に係る契約書に記載されている第六条の二第四号イからハまで及びホに掲げる事項を記載した文書を再受託者に交付すること。
- 三
- 法第十五条の四の五第一項 の許可を受けて輸入された廃棄物の処分又は再生を委託しないこと。
- 四
- 前三号に定めるもののほか、第六条の二第一号、第二号、第四号及び第五号の規定の例によること。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
(昭和四十六年九月二十三日厚生省令第三十五号)
第10条の7
法第十四条第十六項 ただし書の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
- 一
- 中間処理業者から委託を受けた産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、当該中間処理業者が行つた処分に係る中間処理産業廃棄物に限る。以下この条において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分(最終処分を除く。以下この条において同じ。)を次のイからトまでに定める基準に従つて委託する場合
- イ
- 産業廃棄物の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
- ロ
- 産業廃棄物の処分又は再生にあつては、法第十五条の四の五第一項の許可を受けて輸入された廃棄物以外の廃棄物に限り委託することができることとし、かつ、他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
- ハ
- 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、第八条の四で定める書面が添付されていること。
- 委託する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
- 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
- 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力
- 産業廃棄物の処分を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力
- 委託契約の有効期間
- 再委託者(中間処理業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を再委託する者をいう。以下この条において同じ。)が再受託者(再委託者が当該中間処理業者から受託した産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者をいう。以下この条において同じ。)に支払う料金
- 再受託者が産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を受けた者である場合には、その事業の範囲
- 産業廃棄物の運搬に係る委託契約にあつては、再受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地並びに当該場所において保管できる産業廃棄物の種類及び当該場所に係る積替えのための保管上限
- 8.の場合において、当該委託契約に係る産業廃棄物が安定型産業廃棄物であるときは、当該積替え又は保管を行う場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
- 再委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
- (イ)当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
- (ロ)通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
- (ハ)他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
- (ニ)その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
- 受託業務終了時の再受託者の再委託者への報告に関する事項
- 委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項
- ニ
- ハに規定する委託契約書及び書面をその契約の終了の日から五年間保存すること。
- ホ
- あらかじめ、当該中間処理業者に対して再受託者の氏名又は名称(法人にあつては、その代表者の氏名を含む。)及び当該委託がイ又はロに掲げる基準に適合するものであることを明らかにし、当該委託について次に定める事項が記載された当該中間処理業者の書面による承諾を受けていること。
- 委託した産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
- 再委託者の氏名又は名称、住所及び許可番号
- 承諾の年月日
- 再受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号
- ヘ
- ホに規定する書面の写しをその承諾をした日から五年間保存すること。
- ト
- 再受託者に当該産業廃棄物を引き渡す際には、その受託に係る契約書に記載されているハ 1.から4.までに掲げる事項を記載した文書を再受託者に交付すること。
- 二
- 法第十九条の三(第二号に係る部分に限る。)、第十九条の五又は第十九条の六の規定に基づき命令を受けた者が、当該命令を履行するために必要な範囲で、当該者に当該命令に係る産業廃棄物の処理を委託した者の承認を得て他人にその処理を委託する場合
- アジェンダ21
- 油
- 閾値(いきち)
- 委託基準(廃棄物処理法)
- 一般廃棄物
- エコデザイン
- 「炎色反応」とは
- 塩化ビニルモノマー
- 応急の措置(水質汚濁防止法)
- 沖永良部島
- 汚染者負担の原則
- 汚染状況重点調査地域
- 汚染土壌処理業(新法第22条)
- 汚染の除去等の措置
- 汚染廃棄物対策地域
- 汚染廃棄物等
- カーシュレッダーダスト
- カーボンフットプリント(Carbon foot print)
- 改善命令
- 解体自動車
- 拡大生産者責任
- 瑕疵(かし)
- 化審法
- 課電自然循環洗浄法
- 家電リサイクル法
- 家電リサイクル法罰則
- 環境基準(水質汚濁防止法)
- 環境債務
- 環境側面
- 環境デュー・デリジェンス
- 環境パフォーマンス
- 管理票(新法20条)
- 危険物
- 基準発生原単位
- 逆有償
- キャップアンドトレード方式
- 行政代執行
- 許可施設
- 区間委託
- クレジット方式
- クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス
- グリッド法
- 形質の変更
- 形質変更時要届出区域(新法11条)
- 下水道法
- 消印
- 建設リサイクル法
- 原位置封じ込め
- 原位置不溶化・不溶化埋め戻し
- 構造基準(水質汚濁防止法)
- 公布
- 小型電子機器等
- 5点混合法
- 戸別回収
- 混合物(廃棄物処理法)
- サーキュラーエコノミー
- 再委託(廃棄物処理法)
- 再資源化(建設リサイクル法)
- 再資源化(小型家電リサイクル法)
- 再資源化(自動車リサイクル法)
- 最終処分
- 再商品化(家電リサイクル法)
- 再商品化(容器包装リサイクル法)
- 再生利用(食品リサイクル法)
- 錯誤
- 再資源化
- 産業廃棄物
- 産業廃棄物管理票
- (産業廃棄物の)三者契約
- GX(グリーントランスフォーメーション)
- シーベルト
- 事故由来放射性物質
- 施行
- 資産除去債務(環境分野)
- 指示措置(新法7条)
- 資源効率(RE:Resource efficiency)
- 持続可能な開発
- 指定施設
- 指定施設(水質汚濁防止法)
- 自主調査
- 持続可能な開発目標(SDGs)
- 指定調査機関
- 指定廃棄物
- 指定物質
- 指定物質(水質汚濁防止法)
- 指定法人
- 指定有害廃棄物
- 自動車リサイクル法
- 車両制限令
- 重要事項説明
- シュレッダーダスト
- 循環型社会形成推進基本法
- 使用済自動車
- 消防法
- 除去
- 除去実施区域
- 除去土壌
- 食品リサイクル法
- 除染特別区域
- 処分
- 処理
- 処理困難通知
- 水質汚濁防止法 − 法第二条第二項第二号 の政令で定める項目
- 水質汚濁防止法
- 水濁法
- ステーション回収
- ストックホルム条約
- スマートグリッド
- スラグ
- 3R
- 制動距離
- 製品のライフサイクル
- 生物多様性
- 施行
- 線形マルチステージ
- 線量換算係数
- 総合判断説
- 措置内容等報告書
- ダイオキシン類
- 台帳(新法15条)
- 台湾における土壌及地下水汚染整治法
- タダ乗り
- 多量排出事業者(廃棄物処理法)
- 地球温暖化係数
- 中央環境審議会
- 中間処理
- 貯油施設等(水質汚濁防止法)
- 通達
- 「Single-Use Plastic」と「使い捨てプラスチック」
- 積替え保管
- 定期点検(水質汚濁防止法)
- 低濃度PCB廃棄物
- 鉄鋼スラグ
- 電子マニフェスト
- 道路交通法
- 動静脈連携
- 道路法
- 特定一般廃棄物
- 特定再資源化物品
- 特定再資源化等物品
- 特定産業廃棄物
- 特定施設(水質汚濁防止法)
- 特定施設の「使用の廃止」
- 特定事業場
- 特定地下浸透水
- 特定廃棄物
- 特定有害物質
- 特定有害物質を製造、使用又は処理する施設
- 特定有害産業廃棄物
- 土砂運搬車
- 土壌
- 土壌汚染対策法
- 土壌汚染対策法 第31条(指定調査機関の指定の基準) 第2号
- 土壌汚染対策法 第31条(指定調査機関の指定の基準) 第3号
- 土壌汚染対策法 法36条(土壌汚染状況調査等の義務) 第2項
- 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令
- 土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の施行について(通知)
- 土壌汚染の除去措置
- 特別管理産業廃棄物
- 廃棄物
- 廃棄物処理法
- 廃棄物熱回収施設設置者認定制度
- 排出者責任(廃棄物処理法)
- 排出量取引
- 排水基準(水質汚濁防止法)
- 暴露(ばくろ)
- 発がんリスク10-5相当レベル
- パブリックコメント
- パラジクロロベンゼン
- ファクターX
- 微量PCB廃棄物
- フィードインタリフ
- 不確実係数
- 吹き付けアスベスト(資産除去債務関連)
- ブラックカーボン(Black Carbon)
- ブラックマス
- 「プラスチック・スマート」キャンペーン
- フロン回収・破壊法
- ベクレル
- 放射性セシウム濃度
- 放射性物質汚染対処特措法
- 法に基づく調査契機
- ASR
- ASRリサイクル率
- ASR投入施設活用率
- ASTM規格
- CDM(Clean Development Mechanism)クリーン開発メカニズム
- G20資源効率性対話
- MSDS(Material Safety Data Sheet)
- NOAEL(No Observed Adverse Effect Level):無毒性量
- OECD
- PCB(資産除去債務に関して)
- POPs
- RE:Resource efficiency
- SDGs(持続可能な開発目標)
- TDI(Tolerable Daily Intake):耐容一日摂取量
- URS社(旧デイムス・アンド・ムーア社)
- VSD(Virtually Safe Dose):実質安全量
- WEEE(ダブリュートリプルイー)